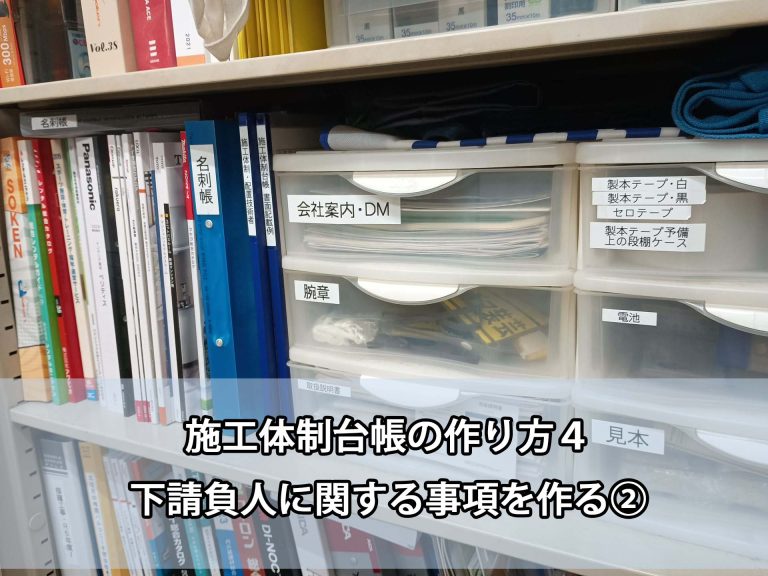現場監督の皆様、下請負業者から提出された施工体制台帳の内容確認に追われ、本来の業務が進まないと悩んでいませんか?
特に「下請負人に関する事項」は項目が多く、どこを重点的にチェックすればよいか分かりにくいものです。
この記事では「下請負人に関する事項」のうち下請業者が記入する欄について、その正しい書き方とチェックすべきポイントを、公共工事の経験に基づいた解説します。
社会保険の加入状況や各種技術者の配置など、法令遵守に不可欠な項目をわかりやすく整理しました。
この記事を読めば、書類チェックの勘所がわかり、差し戻しの手戻りなく、迅速かつ正確に業務を進められるようになります。
この記事は、画像右側の下請け業者に関する箇所の解説をします。
左側の元請業者に関する箇所は、以下の記事を参照してください。
下請負人に関する事項(右側)の記入事項
⑩下請け業者の情報
会社名、代表者名、住所
下請け業者の名称などを記入します。
支社や営業所が別にある会社は、工事を担当している支社、営業所のものを記入します。
本社が工事を担当する場合は、本社の情報になります。
工期、契約日
下請け業者の『工期』欄は、工事全体の工期と違い、実際に下請け業者が工事に関わる期間を記入します。
工期の開始は、一番早いタイミングで「契約を交わした日(注文請負を出した日)」になります。
工期の完了日も下請け業者との契約に依りますが「工事全体の完了検査後に手直しが発生したとき、依頼するかもしれない」などの事を考慮すると、基本的には工事全体の完了日と同じにした方が良いでしょう。
『契約日』の欄は契約書(注文請書)に沿った日付を記入します。
⑪建設業の許可
下請け業者が取得している建設業の許可票について記入します。
「建設業の許可」の趣旨の上では、下請け業者によっては必ずしも必要ではありませんので、
未取得の場合は空欄とします。
取得している場合は必ず書かなければいけません。
建設業の許可票は5年更新制なので有効期間に注意してください。
契約時は期間内でも、工期中に切れてしまう場合は申請書も添付すると良いでしょう。
⑫健康保険の加入状況等
下請け業者の各保険の加入状況と番号(下4桁)を記入します。
建設業界では、小さい会社は低賃金や手続きの煩わしさから各種保険類、
従業員が国民健康保険ですら未加入というケースが多くあり、大きな問題となっています。
仮に未加入だとして「入っていません」では通りません。
元請業者には指導義務があるので、未加入業者がいる場合は下請負契約ができるように保険加入を促しましょう。
雇用保険は、小さな事業所の場合はそもそも雇用者がいない場合のありますので、その場合は『適用除外』となります。
施工体制台帳における健康保険は「事業所単位での加入」の確認のためのものであるため
一人親方に関しては、『適用除外』を〇で囲み、番号は『-』でも良いとされています。
しかし、これは事業者が雇用者を一人親方扱いして経費を削減する、ことを推奨するものではなく
もしそれが明らかになった場合は、罰則を受けることもあり得ます。
参考: 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A(国土交通省) (pdf)
上記リンク先のpdfに、適用除外とできる条件、下請け業者が未加入だった場合の対処、
番号下4桁記入の旨などが記載されています。
⑬下請け業者内の各技術者
現場代理人名
建設業法で定められた現場代理人の名前を記入します。
主任技術者と兼任する事業所も多いと思います。
主任技術者名
主任技術者を配置する場合は、主任技術者の名前と資格内容を記入します。
建設業の許可を取得していない事業者は、その仕組み上必ず空欄となるはずです。
主任技術者についての詳しい要件は、下記を参照してください。
権限及び意見申出方法
ほとんどの場合は『契約書記載の通り』や『書面による』です。
「この役職は、工事のどこまで権限を持っていますか?(口が出せますか?)それはどこで定めていますか?」というニュアンスです。
安全衛生責任者名
労働安全衛生法では、安全衛生責任者は以下の役割を担当します。
要は『職長』です。
事業所の中で、作業の安全管理・労働の安全管理などの責任を持つ者を記入します。
この欄は必ず記載します。
仮に1人しかいない事業所なら、事業主が安全衛生責任者です。
参考: 技術者の役割に応じた配置・専任要件の基本的枠組みの再検討に向けて(国土交通省) (pdf)
安全衛生推進者名
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では仙人が必要になります。
役割は、主に安全衛生責任者の補佐です。
10人以上の大きな規模の場合は、安全衛生責任者が大変だから手伝ってあげましょう。というニュアンスです。
雇用管理責任者名
従業員の雇用について管理している者を記入します。
従業員、社員にとって円滑な雇用環境を提供する役割といったニュアンスです。
一定規模の会社では、人事部が相当するでしょう。
小中規模の事業所では、多くが代表(社長、事業主)がこの役割を務める事になると思います。
専門技術者名
専門技術者とは、主な担当工事とは別で作業を行う場合の技術者を言います。
例えば、下請負業者の担当作業が現場管理、工程管理、施工管理などであるなら、
それとは別で下請負業者が足場の組立てを行う場合は、足場の組立てを行う作業担当者名を書き、
担当工事欄には「足場の組立て」、資格内容には「足場の組立て等作業主任者」が入ります。
専門技術者がいない場合は、空欄で問題ありません。
⑭外国人就業者など
外国人建設就労者の従事の状況(有無)
日本国籍を持たないが在留資格がある作業員、がいるなら「有」となります。
外国人技能実習生の従事の状況(有無)
作業員の在留資格が技能実習の場合は、こちらに「有」を付けます。
まとめ:確認事項
この記事では「施工体制台帳・下請負人に関する事項」のうち、下請業者が記入する欄について、確認すべきポイントを解説しました。
- 建設業の許可: 取得している会社は必ず記入。有効期限は十分かを確認。
- 社会保険: 未加入の場合は指導義務が生じるため、その理由(適用除外など)が正当かを確認する。
- 各種技術者: 現場代理人、安全衛生責任者がいるかどうか。
- 主任技術者は、建設業の許可がある場合、必ず配置が必要。
- 主任技術者の資格要件を満たしているかどうか。
- 安全衛生推進者:常時10人以上50人未満なら配置が必要。
内容の手落ちは後々の発注者からの是正指導に繋がります。
本記事と書類を見比べて確認業務の効率化と品質向上に利用してください。