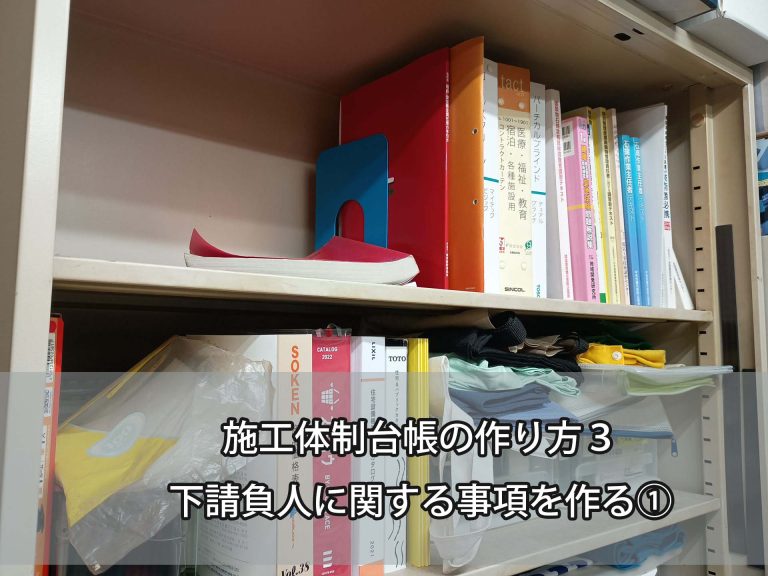施工体制台帳の中で、工事ごとに違った内容を記入しないといけない『下請負人に関する事項』の作成に時間を取られていませんか?
「健康保険の加入状況?」「主任技術者と監理技術者?」作成のたびに記入欄1つ1つの内容を調べていては、手間が掛かってしまいます。
この記事は『下請負人に関する事項』の正しい書き方、記入欄の埋め方について解説します。
このページを見ながら作れば、面倒な記入作業が素早く終わります。

元請業者分(左側)の書き方
この記事では、画像左側の元請業者に関する箇所の解説をします。
右側の下請け業者に関する箇所は、以下の記事を参照してください。
『下請負人に関する事項』の体裁は国土交通省から無料でダウンロードできます。
テンプレートを持っていない場合は、使わせてもらいましょう。
① 作成日
『下請負人に関する事項』の作成日を記入します。
ここで言う作成日とは「書き終えて提出できる状態になった日」ですので、矛盾ができないように注意してください。
例えば
『作成日が下請け業者の請負日より前』→なぜ未来の下請負契約日が予測できたのか?
『作成日が下請け業者の着手日より後』→作業に入った後で契約したのか?
など、不自然がないように作成してください。
②会社名と事業所名
『会社名』は契約書に記載されている、工事を受注した組織を記入します。
御社の会社名はもちろん、支社や営業所名も含めて契約している場合は、そこまで記入します。
『事業所名』は、いわゆる工事本部の名称を書きます。
明確な定義はありませんが、工事現場に監督が常駐する事務所を作るようなら
「〇〇工事 現場事業所」
現場が会社の近辺や小規模な工事で現場事務所を設置しない、
などの理由で会社事務所を本部として扱うようでしたら「本社」のように記入します。
③建設業の許可
取得している建設業の許可票の情報を記入します。建設業の許可票は別途でコピーを添付するので、同じ内容をそのまま書き写して問題ありません。
複数の許可を取得している場合は、わかる範囲で省略した名称で記入するのが通例となっています。
(建築一式→建築or建、とび・土工→と、など)
書ききれない場合は、請け負った工事に必要な許可のみを記入します。
建設業の許可は5年更新制なので、有効期限に注意してください。
工期内で期限が切れると、指摘の対象となります。
④工事内容
工事名称及び工事内容
工事の件名と概要を2〜3行程度でまとめます。
工事の全貌を文章にすると間違いなく枠が足りませんので、要点のみを書き記してください。
それに加えて、元請業者の担当業務を記入します。
元請業者でしたら
「現場管理・安全管理・工程管理・工事写真台帳作成・工事書類作成」
あたりになるのではないでしょうか。
発注者及び住所
工事の発注者の情報を記入します。
発注者と交わした契約書の内容を書き写して問題ありません。
公共工事の場合、発注部署と担当部署は違う事が多いので注意してください。
この欄に記入するのは発注者なので「〇〇市 契約課長 〇〇」や「〇〇株式会社 契約担当 〇〇」のようになる事が多いと思います。
工期、契約日
工期と契約日は、発注者と交わした契約書の内容を書き写します。
発注機関や契約時期によって「契約日から工期が開始」「工期の開始は契約の翌日から」や、「休日を挟むので明けから工期開始」のように違いがあるので注意してください。
⑤契約営業所
元請契約
発注者と請負契約を結んだ、元請負業者の社名を記入します。
発注者と交わした契約書に記載されています。
下請負契約
一次下請負業者と契約を結んだ事業所名を記入します。
大きな会社で『発注者との契約は本社が行い、下請負業者との契約は支社が行う』などの場合に用います。
そうでない場合は『同上』で問題ありません。
⑥健康保険等の加入状況
保険加入の有無
健康保険・厚生年金保険・雇用保険
この欄は、原則全て『加入』です。
元請業者ならば法的な『適用除外』でない限り「入っていません」では済まされないと思います。
(例えば役員のみの会社で「会社員」がいなければ、雇用保険は入れないので『適用除外』です。)
加入している保険の種類、組合名と番号の下4桁を記入します。
参考: 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A (pdf)
上記リンク先のpdfに、適用除外とできる条件、未加入者への対処、番号下4桁記入の旨などが記載されています。
事業所整理番号等
各保険の番号を記入します。
適用除外の場合は『適用除外』と書いておけば問題ないと思います。
下請契約
⑤契約営業所 の欄と同様に、本社と支社で別々の保険番号がある場合は記載します。
⑦発注者の監督員
発注者の監督員名
発注者側の機関から担当として就く、監督員の名前を記入します。
監督員が正式に配属されない案件では、工事の出来栄えを確認してくれるお客側の担当者で良いと思います。
権限及び意見申出の方法
公共工事であれば契約書に記載があると思います。
『監督員は工事に対するどこに強制力を持つか』『それはどこに記されているか』というものです。
⑧元請業者の各技術者等
監督員名
発注者の監督員ではありません。
「元請業者欄の監督員って何のことだ?」と思うかもしれませんが、この欄には「下請け業者に対しての契約内容や施工方法を監督する人」の名前を記入します。
要は監督そのものです。
現場代理人名
建設業法で定められた現場代理人の名前を記入します。
監督員と同じ人が担当する事も多いと思います。
監理技術者名 主任技術者名
この工事を担当する主任技術者・監理技術者の氏名を記入します。
主任技術者・監理技術者は、他社の人間ではなく受注している会社に所属している者でないといけません。
詳しい要件は以下を参照してください。
権限及び意見申出方法
ほとんどの場合は『契約書記載の通り』や『書面による』です。
「この役職は、工事のどこまで権限を持っていますか?(口が出せますか?)それはどこで定めていますか?」というニュアンスです。
ほぼ建前だと思います。
専門技術者名
専門技術者とは、主な担当工事とは別で作業を行う場合の技術者を言います。
例えば、元請業者の担当作業が現場管理、工程管理、施工管理などであるなら、
それとは別で元請業者が足場の組立てを行う場合は、足場の組立てを行う作業担当者名を書き、
担当工事欄には「足場の組立て」、資格内容には「足場の組立て等作業主任者」が入ります。
専門技術者がいない場合は、空欄で問題ありません。
⑨外国人就業者など
外国人建設就労者の従事の状況(有無)
日本国籍を持たないが在留資格がある作業員、がいるなら「有」となります。
外国人技能実習生の従事の状況(有無)
作業員の在留資格が技能実習の場合は、こちらに「有」を付けます。
参考:関連法規
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。